京都写真集 マガジン25号 26号 27号 28号 29号
東山区北部 大谷本廟 六波羅蜜寺 法観寺 六道珍皇寺 清水寺
双林寺 長楽寺 白川 法勝寺跡
東山区南部 泉涌寺 今熊野神社
風あらみこずゑの花のながれきて庭に波立つしら川の里 27ページ
白河の梢をみてぞなぐさむる吉野の山にかよふ心を 30ぺージ
白河の春の梢のうぐひすは花の言葉を聞くここちする 31ページ
波もなく風ををさめし白川の君のをりもや花は散りけむ 36ページ
1 世にあらじと思ひける頃、東山にて、人々霞によせて
思をのべけるに 19ページ
そらになる心は春の霞にてよにあらじとも思ひたつかな
2 いにしへごろ、東山にあみだ房と申しける上人の庵室にまかりて
見けるに、あはれとおぼえてよみける 165ページ
柴の庵ときくはいやしき名なれども世に好もしきすまひなりけり
3 東山にて人々年の暮れに思ひをのべけるに 104ページ
年暮れしそのいとなみは忘られてあらぬさまなるいそぎをぞする
4 上西門院の女房、法勝寺の花見られけるに、雨のふりて暮れ
にければ、歸られにけり。又の日、兵衛の局のもとへ、花の御幸
おもひ出させ給ふらむとおぼえて、かくなむ申さまほしかりし、
とて遣しける 27ページ
見る人に花も昔を思ひ出でて戀しかるべし雨にしをるる
5 白河の花、庭面白かりけるを見て 27ページ
あだにちる梢の花をながむれば庭には消えぬ雪ぞつもれる
6 世をのがれて東山に侍る頃、白川の花ざかりに人さそひければ、
まかり歸りけるに、昔おもひ出でて 28ページ
ちるを見て歸る心や櫻花むかしにかはるしるしなるらむ
7 八條院の宮と申しけるをり、白川殿にて蟲あはせられけるに、
かはりて、蟲入れてとり出だしける物に、水に月のうつりたる
よしをつくりて、その心をよみける 170ページ
祇園白川
山家集には白川の歌・詞書がいくつか出てきます。でもこのあたりと
解釈するには無理があります。岡崎に六勝寺があり、白川御所は
その近くでした。ですから、山家集にある白川は現在の岡崎あたりと
みるのが自然です。




「かにかくに祗園はこひし寝るときも枕の下を水のながるる」 吉井勇
11月8日に「かにかくに祭」があり、舞妓さんたちでにぎわいます。
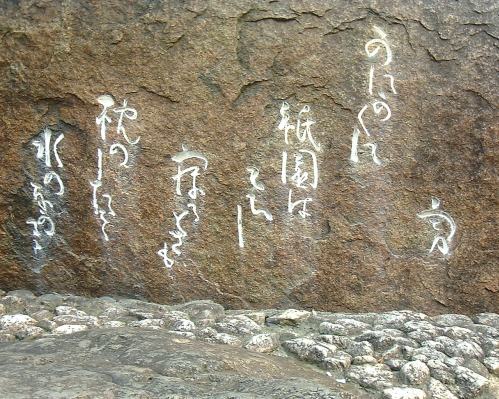
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
長楽寺
長楽寺にて、夜紅葉を思ふといふことを人々よみけるに 90ページ
よもすがらをしげなく吹く嵐かなわざと時雨の染むる紅葉を
長楽寺の創建は桓武天皇の勅願により、最澄が造営したとも言われますが、
諸説があるようです。もともとは広いお寺だったようですが、すぐ東隣の東大谷墓苑
を作るときに寺域を削られたそうです。
建礼門院平徳子は平家滅亡後に、この寺で落飾しました。
紅葉の名所で、山家集にも90Pに「長楽寺にて、夜紅葉を思ふ・・・」
と記されています。


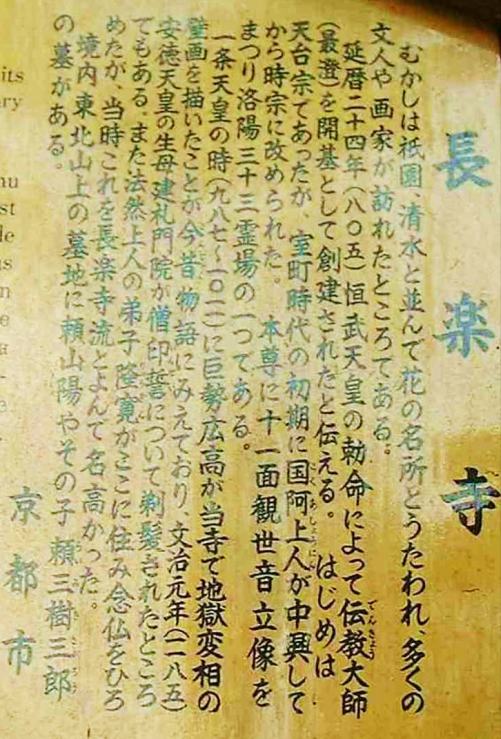
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
双林寺
1 雙林寺にて、松河に近しといふことを人々のよみけるに 260ページ
衣川みぎはによりてたつ波はきしの松が根あらふなりけり
2 野の邊りの枯れたる草といふことを、双林寺にてよみけるに 93ページ
さまざまに花咲きたりと見し野邊の同じ色にも霜がれにけり
西行の時代の双林寺は広大な寺域を誇っていました。今の円山公園から
高台寺あたりまでありました。高台寺の創建で寺域を削られ、かつ明治になって、
円山公園を作るためにも削られてしまって、今は小さなお寺で、西行当時を
しのぶよすがとてありません。

下の本堂以外に堂宇はありません。この堂の左側に「頓阿」と彫られた
小さい墓石があります。二基並んでいて、もう一つは西行のもののはず
ですが、風化して、判読できません。

西行庵、芭蕉庵も当時は双林寺の敷地内にありました。今は飛地のようです。
西行物語では、西行は河内の弘川寺からここに戻って入寂したとあります。
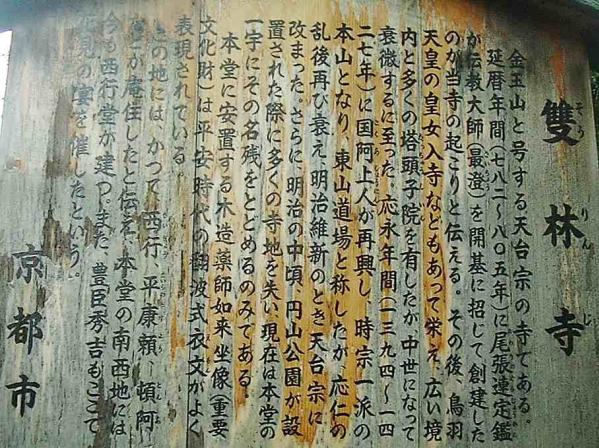
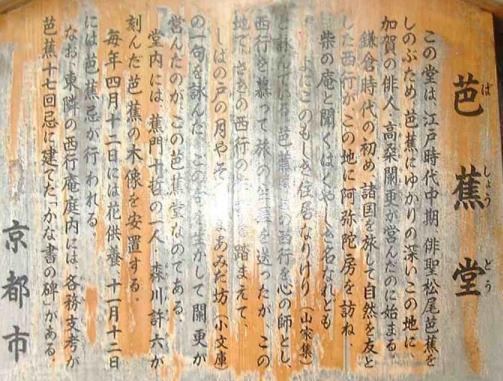
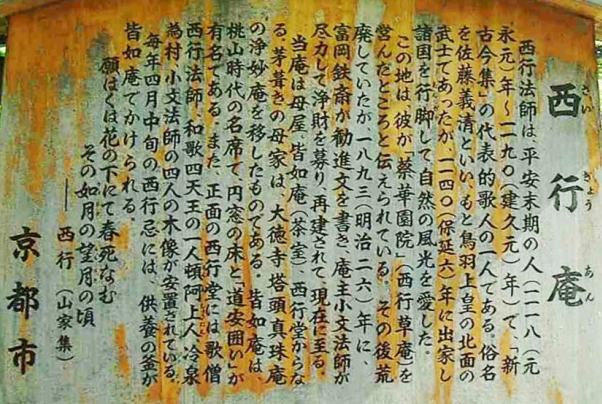
次のページ このページの先頭